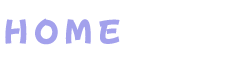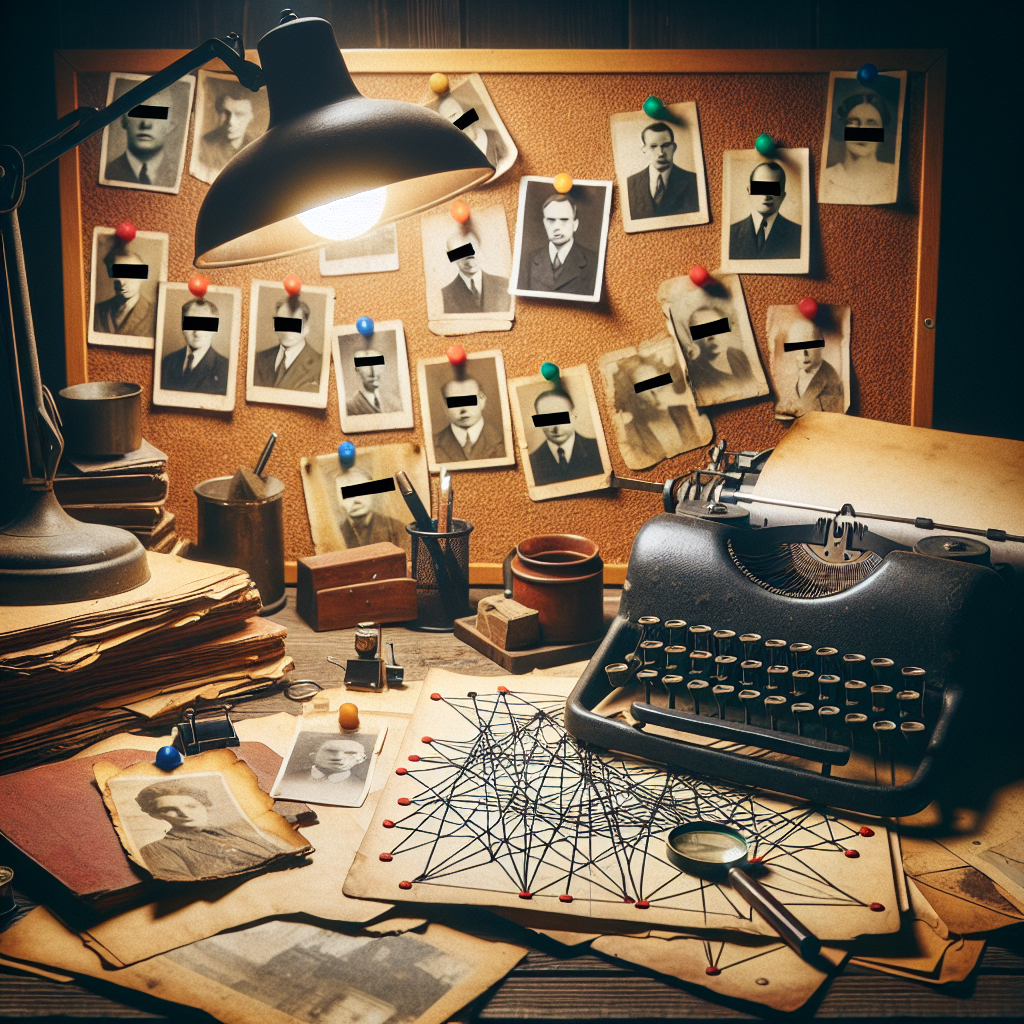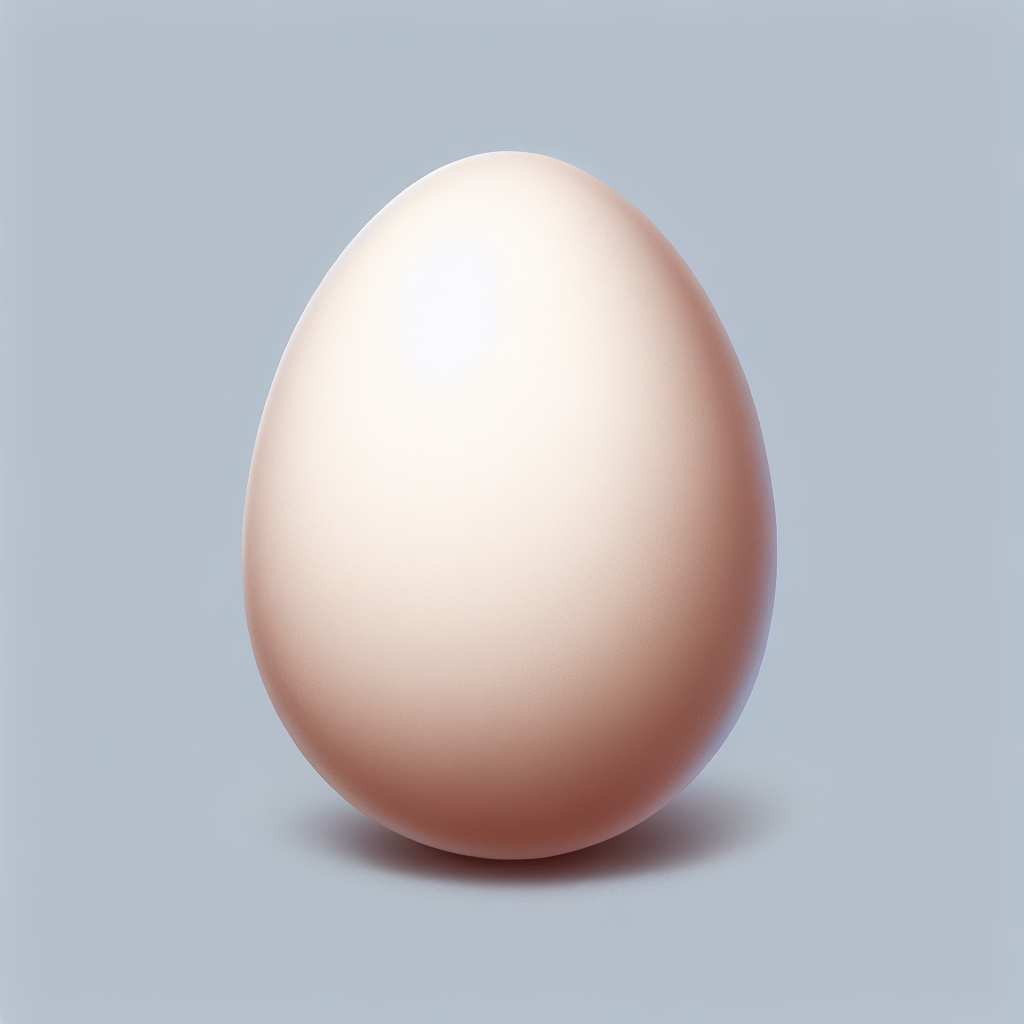1. 共同親権とは
 |
「共同親権」来年4月から運用 「法定養育費」の導入も閣議決定 法務省 改正民法では、離婚後に両親が親権を維持する「共同親権」の導入が盛り込まれています。 単独親権か共同親権かは、両親が協議して決めますが、協議ができない… (出典:テレビ朝日系(ANN)) |
|
共同親権(英:Joint custody)とは、両方の親に親権が与えられる親権形態である。共同親権は、共同身体的親権、共同法的親権、またはその両方を合わせたものを指す場合もある。 共同法的親権では、子どもの両親が、例えば教育、医療、宗教的な養育などに関する主要な意思決定を共有する。共同親権…
53キロバイト (7,834 語) - 2025年8月20日 (水) 03:02
|
共同親権という制度は、親が離婚後も共に子供の親権を持つことを認める法律制度です。以前の日本の法律では、離婚後はどちらかの親が単独で親権を持つことが一般的でした。しかし、家庭内の変化とともに、親が共に関与することの利益が認識され始めました。改正された法律により、2026年4月から日本においても離婚後の共同親権が施行されることになります。共同親権の導入により、両親は離婚後も共に子供の成長に関与し続けることができます。
共同親権の意義は、子供が両親の愛情と養育を継続的に受けることができるという点にあります。これにより、子供の心理的および社会的な安定が保たれるようになります。また、親が子供に積極的に関与することで、子供の幸福度が高まるとも言われています。この制度は、親が離婚後にどのように子供の養育に関わるかについて、より柔軟な選択肢を提供します。
共同親権が成立するためには、両親の合意が必要です。離婚時に、両親が協力して子供の最善の利益を考慮し、共同か単独かを選択することが求められます。合意に至らない場合は、家庭裁判所が子の利益に基づいて判断することになります。このプロセスは、子供の生活において重要な決定を適切に行うことを目的としています。
2. 2026年からの変更点
 |
離婚後の共同親権、2026年4月スタート 単独と選択可 政府決定 …施行日以降であれば、単独親権から共同親権への変更も可能となる。 親権は未成年の子に対して親が持つ権限と義務。共同親権をとった場合、子に関する重要な決… (出典:毎日新聞) |
|
実親子関係の場合 子の実父母が共同して親権を行使する(818条第3項本文)。ただし、後述のように一方が親権を行使できないときや両親が離婚したときには単独親権となる。 養親子関係の場合 子が養子であるときは、養親の親権に服する(818条第2項)。したがって、実親の親権…
47キロバイト (7,815 語) - 2024年10月29日 (火) 16:22
|
2026年4月から、離婚後の共同親権が正式に施行されることになりました。
この改正民法の施行により、これまでの単独親権制度が大きく変わることになります。施行日前は、離婚した夫婦のどちらか一方が単独で親権を持つことが一般的でした。
これにより、片方の親が親としての権利や義務を果たすためのアクセスが制限されることが少なくありませんでした。
この改正民法の施行により、これまでの単独親権制度が大きく変わることになります。施行日前は、離婚した夫婦のどちらか一方が単独で親権を持つことが一般的でした。
これにより、片方の親が親としての権利や義務を果たすためのアクセスが制限されることが少なくありませんでした。
しかし、改正民法では、離婚後も両親が共同して親権を持つことが可能となり、両親が協力して子供の成長をサポートできる環境が生まれます。
新たな制度では、両親が話し合いによって共同親権を選択することが可能となり、合意が得られない場合は、家庭裁判所が子供の利益を最優先に考慮して判断することになります。
新たな制度では、両親が話し合いによって共同親権を選択することが可能となり、合意が得られない場合は、家庭裁判所が子供の利益を最優先に考慮して判断することになります。
共同親権をとることで、『日常の行為』、『急迫の事情』など、一方の親が単独で親権を行使出来る旨も定めている。具体例を出すことでトラブルがなくなるように法改正されている。しかし、虐待や家庭内暴力などの恐れがある場合は必ず単独親権をとるように規定されている。この変更により、実際に子供の福祉がどのように向上するのか、また親権者と子供との関係がどのように変わるのかについて大きな注目が集まっています。
【両親の合意が必要な例】
子供の進学先・引越し・重大な医療行為など
【単独で判断できる例】
「日常の行為」食事や習い事の選択・アルバイトなど
「急迫の事情」緊急の医療行為・虐待・事故など
親権を協議する際のポイントとして、親同士の合意が一層重要となり、子供の教育や生活環境の向上につながることが期待されています。
法定養育費の導入も同時に進められることで、経済面でも子供の安定した生活が支えられるでしょう。
この変化は、離婚後の親子関係を再定義するものとなり、社会全体に対しても大きなインパクトを与えることが予見されます。
今後も、この制度がどのように進化し、社会にどのような影響を及ぼすのか、引き続き注視していく必要があります。
この変化は、離婚後の親子関係を再定義するものとなり、社会全体に対しても大きなインパクトを与えることが予見されます。
今後も、この制度がどのように進化し、社会にどのような影響を及ぼすのか、引き続き注視していく必要があります。
3. 法定養育費の導入
 |
共同親権、来年4月施行 法定養育費も導入 …定させる狙いがある。 共同親権か単独親権かは、離婚時に父母が協議して選択。意見が一致しなければ家庭裁判所が判断する。共同親権では、進学や転居など子の… (出典:時事通信) |
|
費、医療費などが該当する。典型的には、離婚によって一方の親のみが親権を行うことになった場合に、親権者でなくなった親が支払う義務を負った費用を養育費と呼ぶ。ただし、婚姻関係は養育費の要件ではなく、子供を養育している親は、何らかの事情で別居している他方の親から養育費を受け取ることができる。 養育費…
43キロバイト (6,753 語) - 2025年10月24日 (金) 22:33
|
新たな制度の導入として注目されているのが法定養育費です。
法律で定められた20,000円を基に、親が子供の養育に必要な費用を負担する仕組みとなっています。
この制度は、養育費の未払い問題を減少させることを目的としており、より安定した子供の生活環境を確保する役割を果たします。共同親権制度の一環として、この養育費制度がどのように機能するかが注目されています。
法律で定められた20,000円を基に、親が子供の養育に必要な費用を負担する仕組みとなっています。
この制度は、養育費の未払い問題を減少させることを目的としており、より安定した子供の生活環境を確保する役割を果たします。共同親権制度の一環として、この養育費制度がどのように機能するかが注目されています。
共同親権との関係性については、離婚後も両親が子供の養育に責任を持ち続けるための新たな枠組みが形成されつつあります。
共同親権が導入されることで、これまでは母親が多くを担っていた養育の責任を、父親と分担することが可能になります。このことは子供にとっても、より豊かな育成環境を提供することにつながるでしょう。
特に、共同親権によって父親も積極的に子供の生活に関与することを促すことが重要であり、これが法定養育費の考え方とも一致しています。
共同親権が導入されることで、これまでは母親が多くを担っていた養育の責任を、父親と分担することが可能になります。このことは子供にとっても、より豊かな育成環境を提供することにつながるでしょう。
特に、共同親権によって父親も積極的に子供の生活に関与することを促すことが重要であり、これが法定養育費の考え方とも一致しています。
また、この新しい制度が確立されることで、親が養育費の支払いを怠った場合には法的に対処する手段が強化されます。この点においても、子供の生活がより安定することが期待されています。さらに、法定養育費が導入されることにより、親はあらかじめ決められた額を支払うことが義務付けられるため、争いごとを減らすと同時に子供の成長を左右する重要な要素となります。
4. 最後に
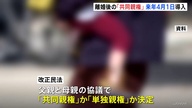 |
「共同親権」来年4月1日から導入 政府が閣議決定 離婚後の子どもの親権「父親と母親の両方」が可能に …離婚後の子どもの親権を父親と母親の両方に認める「共同親権」について、政府は来年4月1日から導入することを決めました。 現行の民法では、離婚後は父親と… (出典:TBS NEWS DIG Powered by JNN) |
|
離婚で両当事者ともに離婚に合意をしているが外国での離婚承認を得るために審判離婚(裁判所の判断による離婚)による必要がある場合などに利用されている。 協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚すること。裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度である。 離婚…
104キロバイト (16,362 語) - 2025年6月29日 (日) 01:59
|
新制度である離婚後の共同親権について、そのメリットと課題を見ていきましょう。
まず、この制度により、離婚した夫婦が共同で子供の親権を持つことが可能となります。
このことは、子供の福祉を一層考慮した選択肢を提供するものとして期待されています。
また、共同親権制度のもとでは、両親が協力して子供の成長を支え合うことができるため、子供にとってはより良い環境が提供されるでしょう。
ただし、両親の協議がうまくいかない場合には、家庭裁判所が親権者を決めることになるため、法的な調整が必要なケースも出てくるでしょう。
さらに、今後の見通しとしては、この共同親権制度の普及とともに、家庭内での親のパートナーシップや法的なサポート体制の整備が求められるでしょう。
このことは、子供の福祉を一層考慮した選択肢を提供するものとして期待されています。
また、共同親権制度のもとでは、両親が協力して子供の成長を支え合うことができるため、子供にとってはより良い環境が提供されるでしょう。
ただし、両親の協議がうまくいかない場合には、家庭裁判所が親権者を決めることになるため、法的な調整が必要なケースも出てくるでしょう。
さらに、今後の見通しとしては、この共同親権制度の普及とともに、家庭内での親のパートナーシップや法的なサポート体制の整備が求められるでしょう。
具体的には、共同親権における合意形成の促進や、親権を共有するための条件を詳細に見直すことが必要です。
今後、制度の実施にあたっては、制度の運用状況を定期的に見直しながら、よりよい制度作りを進めていくことが肝要です。
今後、制度の実施にあたっては、制度の運用状況を定期的に見直しながら、よりよい制度作りを進めていくことが肝要です。
最後に、この新制度のメリットを最大限に活かすためには、制度に対する理解を深め、親同士の協力体制を強化することが重要であると考えます。