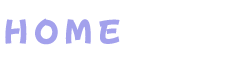1. 駄菓子の歴史と社会的役割
 |
駄菓子がどんどん消えていく──「糸引き飴」終売だけじゃない業界の苦境 「懐かしい」は残酷な言葉だった …ディ」や“10円当たり飴”も、2021年のメーカー廃業により終売に。そして、駄菓子ではないが駄菓子屋の名物商品だった「ようかいけむり」も、2020年に… (出典:集英社オンライン) |
昭和時代から親しまれてきた駄菓子。小さな子どもたちにとって、駄菓子屋に足を運ぶことは特別な冒険でした。小銭を片手に友達と相談しながら選ぶ駄菓子は、ただの食べ物以上の存在で、友情を深めるツールでもありました。また、駄菓子屋のおばちゃんやおじちゃんから教わる地域の知恵やマナーは、グローバル社会における教育の一環としての役割を担っていました。
しかし、現代では地域の駄菓子屋が次々と姿を消し、多くの駄菓子が市場から消えていっています。この変化の背景にあるのは、原料の高騰や小規模メーカーの廃業など、経済的な要因が大きいのです。そして、駄菓子文化の変遷は、地域社会そのものの変化を反映しています。
駄菓子が持つ教育的価値や地域の絆を再評価し、新しい時代に即した駄菓子文化のあり方を模索することが求められています。そのためには、地域社会全体で駄菓子文化を次世代にどう伝えていくかが鍵となるでしょう。
2. 経済的背景:原料高騰と業界の苦境
 |
駄菓子屋で100円あったら何に使う? 芸人・金属バットが忘れられない「うまい棒」の一番おいしい味 …金属バットの「酒辛肉鮪」#41かつて駄菓子屋で親しまれた「糸引き飴」を国内で唯一生産していたメーカーが廃業するなど、物価高騰のあおりを受けて駄菓子の… (出典:集英社オンライン) |
さらに、駄菓子業界全体の収益も年々減少しています。大手菓子メーカーと違い、駄菓子業者の多くは家族経営や小規模な工場で運営されています。大手がコスト削減やスケールメリットを活用できるのに対し、小規模業者は価格競争にさらされ、生き残るのが難しくなっています。そして、消費者の嗜好も変化しています。健康志向の高まりや、嗜好品の多様化により、昔ながらの駄菓子は徐々に市場から姿を消しています。
駄菓子業界の未来は危機に瀕していますが、それでも情熱を持った新しい創業者が現れた、業界を蘇らせる可能性もあります。未来の駄菓子は懐かしさと新たな価値を融合させることで、再び人々に愛される存在になるかもしれません。
3. 耕生製菓の廃業が与えた衝撃
 |
原料高騰で…駄菓子の定番「糸引きあめ」、唯一のメーカーが廃業 …、5月末で終了した。国内唯一のメーカーだった耕生製菓(愛知県豊橋市)が、原料の高騰や工場の老朽化などで廃業したためだ。夫の津野耕一郎社長(72)と一緒… (出典:毎日新聞) |
|
駄菓子(だがし)とは、茶席や贈答にも使われる高級菓子に対し、主に子供向けに製造販売される、安価な菓子のことである。 元禄年間の大坂で、当時は輸入品であった高価な砂糖を使って作られた上菓子に対して、国産の安価な黒砂糖を使用して作られた菓子を「雑菓子」と言い、これが駄菓子…
12キロバイト (1,471 語) - 2025年7月7日 (月) 07:38
|
愛知県豊橋市に位置する耕生製菓が、2025年春に廃業することを決断しました。このニュースは、地元住民と駄菓子好きの人々にとって大きな衝撃を与えており、また昭和から続いてきた「糸引き飴」の終焉を意味しています。
耕生製菓は、多くの子どもたちにとって懐かしい思い出の一部であり、地域の文化として生き続けてきた存在です。そのため、この工場が閉鎖されることに対して、地域住民からは寂しさと共に、地元が失うものの大きさを痛感する声が多く聞かれます。駄菓子業界全体では、原料価格の高騰や後継ぎ不足などが経営を圧迫する要因となっており、耕生製菓も例外ではありませんでした。
特に、糸引き飴はそのユニークな食感と甘さから多くの支持を集めていました。この商品が市場から消えることは、ただ一つの商品の終売以上の意味を持っています。一つの時代が終わりを告げるように、昭和時代の象徴ともいえるこの駄菓子の生産終了は、多くの人々の心にさまざまな感情を呼び起こしています。地元住民や耕生製菓のファンからは、復活を望む意見や、なんとか文化を守ろうという声も上がっています。
駄菓子が次第に市場から姿を消していく中で、耕生製菓の閉業は、地域全体における駄菓子文化の存続に対する意識を新たにする機会となりました。未来へと繋げるためにどのような方策が講じられるべきか、今、問われています。
4. 懐かしさと現実のギャップ
|
糸ひきあめ(いとひきあめ)とは、耕生製菓(愛知県豊橋市)が販売する飴の内部から長い糸が通った駄菓子のこと。正式な商品名は「コーセー 糸引き飴」。 この飴は駄菓子屋に置いてあることが多く、糸を束ねてある中から1本を選んで引き、引き上がった飴が貰える(1回10円)。飴は大小さまざまなサイズがあり、色や味…
2キロバイト (394 語) - 2025年7月13日 (日) 10:40
|
駄菓子と聞くと、多くの人が幼い頃の甘酸っぱい思い出を思い出すことでしょう。駄菓子屋に寄り道をして、わずかなお小遣いでたくさんのお菓子を選ぶ楽しさは、子ども時代特有のものでした。しかし、この懐かしさは現実の厳しさをも映し出しています。現代では、駄菓子業界が厳しい現状に直面しており、多くの伝統的な商品が市場から姿を消しつつあります。代表的なのは、「糸引き飴」で、これを唯一生産していた愛知県豊橋市の耕生製菓は、その歴史に幕を下ろしました。 原料の高騰や消費者の嗜好の変化といった現実が、その背後にあります。
若い世代との接点を見つけることも課題です。現在の若者は、豊富な選択肢に溢れるお菓子市場の中で育ち、駄菓子に対して強いノスタルジーを抱くことは少ないかもしれません。新しい顧客層を獲得するためには、駄菓子の新たな魅力や価値を発信していくことが重要です。同時に、製造コストの見直しや、地域との連携を深めることで、駄菓子本来の魅力を伝え続けることが必要です。地域のイベントに参加したり、地元の学校と連携して駄菓子体験を提供するなど、新しい形での駄菓子文化の継承が求められています。